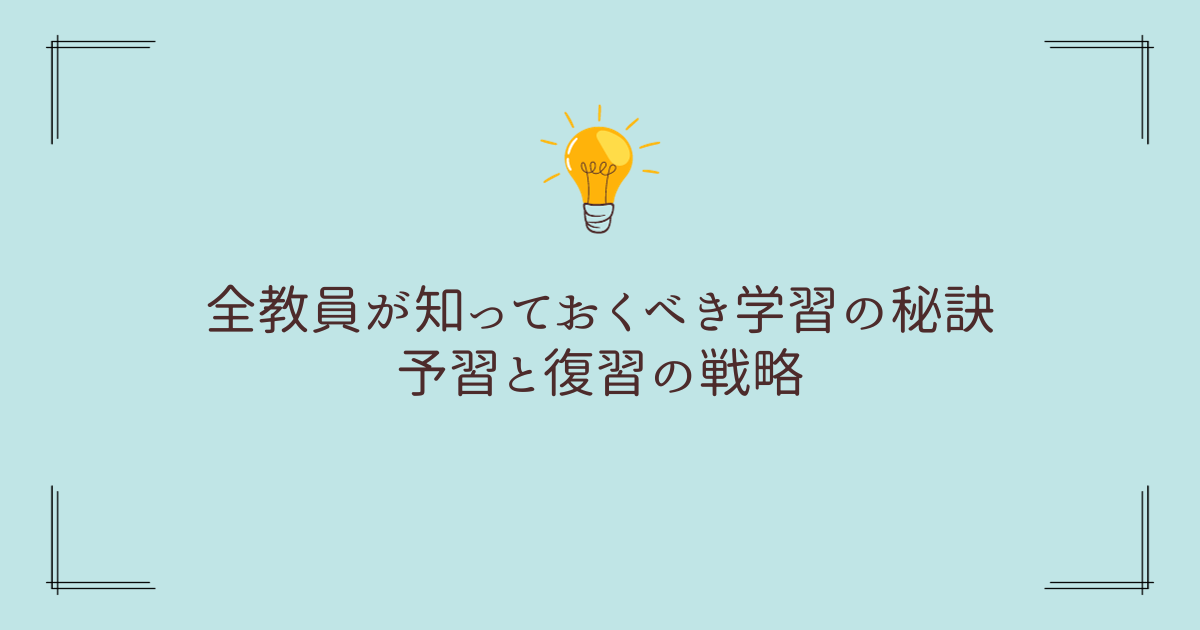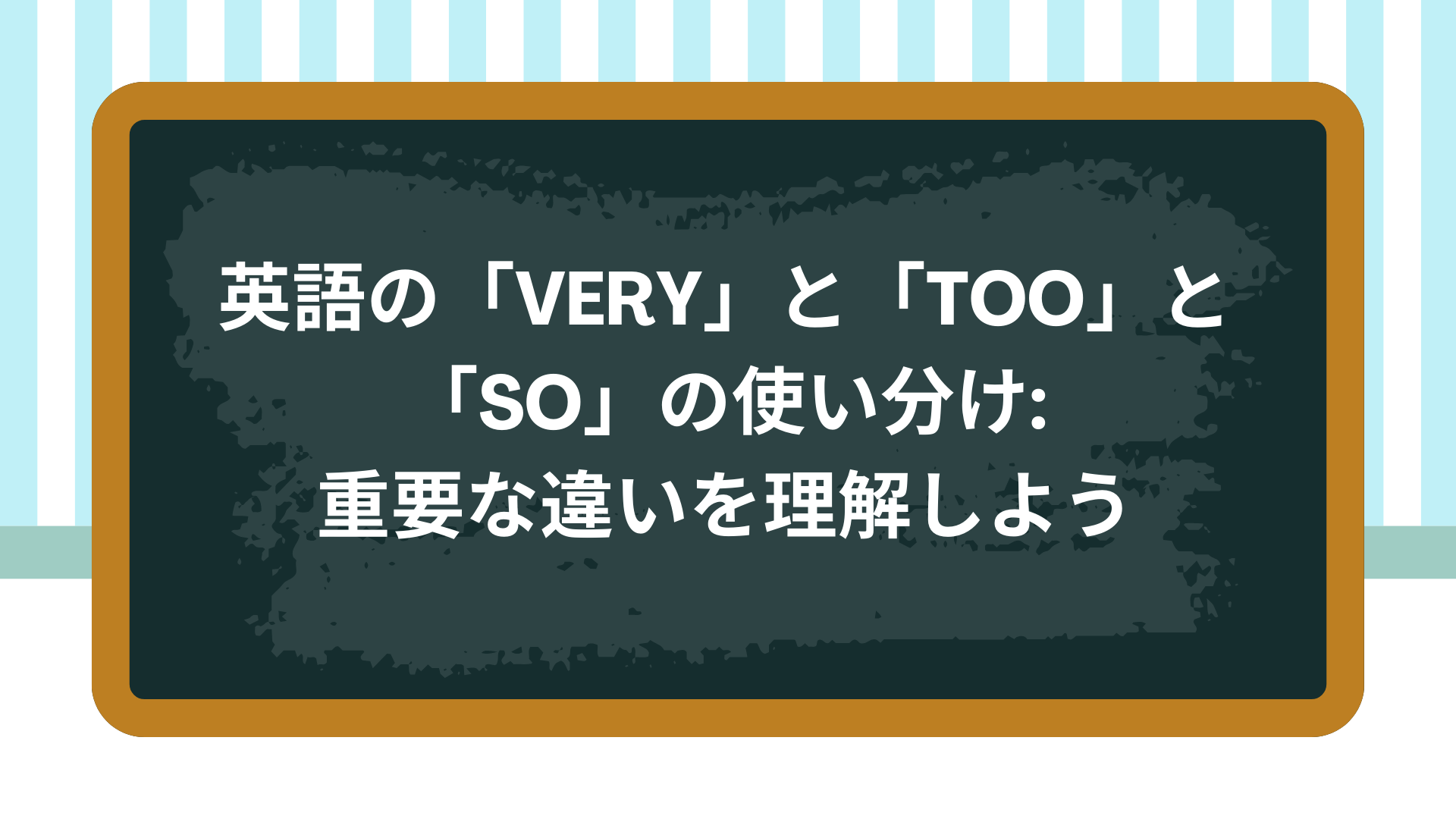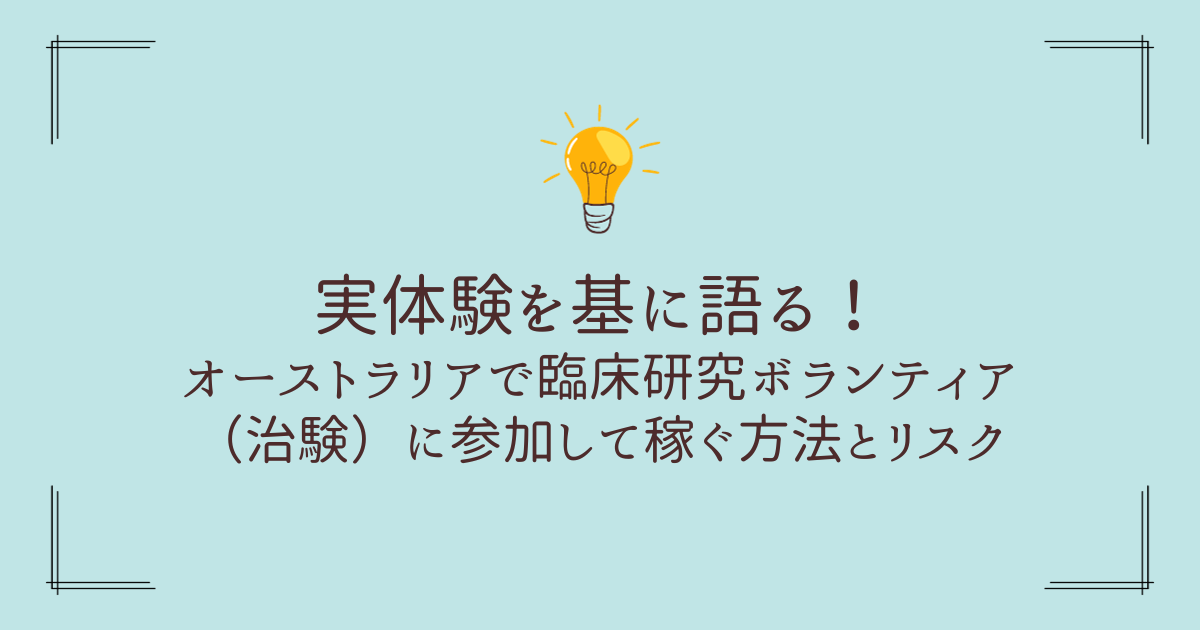学校の先生はよく予習復習をしなさいというけど、実際どっちが大切なんですか?
正直、予習と復習両方している暇なんてないし、やれといわれてもやり方がわかりません。
確かに予習と復習は大事です。それは間違いありません。しかし、それぞれがもたらす効果は違います。それをわかったうえで生徒に伝えられるとより信頼度が増しますよね。
- 予習と復習の効果
- 予習と復習どちらを優先すべきか
- 予習には「新しい情報を理解しやすくなる」という効果がある
- 復習には「記憶を定着させる」という効果がある
- 予習と復習どちらも大切。効果を整理して生徒に伝えることが大事。
予習の効果
予習はなぜ大事なのでしょうか。
その理由は、予習が「新しい情報を理解するための準備」だからです。
新しいことを覚えるのって負担がかかりますよね。
例えば、野球のルールを全く知らないで野球観戦に行ったとしましょう。
ルールは観ながら覚えることになります。そうすると肝心の試合に集中することができなくなります。
しかし、事前に野球のルールを頭に入れて観戦に行けば、試合中にルールを覚える必要はありません。
そうすれば、楽しむポイントや熱くなるポイントがわかるので、より試合自体を楽しむことができます。
そういった準備が学習にも必要です。
その授業を受けるうえでの必要な知識を事前に頭に入れておく。
そうすれば授業でポイントとなる部分にだけ集中することができるので、より授業を深く理解することができる。
復習は、大事なポイントをより深く理解するための準備なのです。
授業中に理解できると自分の自信につながります。
自分は勉強ができる、というマインドを持つことでより勉強が楽しくなります。
どのように予習をすればいいのか
ポイントは予習が新しい情報を理解するための準備だということです。
予習の方法をいくつか紹介します。
- 教科書を読み初めて聞く言葉や知らない単語の意味を事前に調べておく
- 予習用のノートを用意し、自分なりにまとめる
- 教科書やワークなどを解いておき、わからない部分を明確にさせておく
- どんな授業になるか想像してみる
新しいことなのでわからない部分があって当然です。
そこで理解しようとはせずに、ここがわからないんだな、というのを整理しておきましょう。
習ったけど定着していない、けど次の単元で必要な知識については、これを機に復習しましょう。
復習の効果
それでは、復習はなぜ必要なのでしょうか。
大雑把に言うと、復習は「記憶を定着させ、忘れにくくする」効果があるから必要なのです。
前提として、人間は忘れる生き物です。
昨日食べたものさえも忘れます。10秒前に言ったことでさえ忘れてしまうことがあります。
それは、自分の脳がその記憶を、「大事ではないボックス」に入れるからです。
そして多くのものがその「大事ではないボックス」に入れられます。
しかし、同じことを繰り返し行うことで、ある日脳が考えます。
あれ、もしかしてこれは大事なものなのでは?と。
その時初めてその記憶は「大事ボックス」に格納されるわけです。
その関係を短期記憶と長期記憶と言います。
有名なのはヘルマン・エビングハウスの忘却曲線です。
この理論は、人は物事を忘れるといいたいのではなく、復習することが記憶を定着させるうえで大事である、といっているのですが、復習をしなければ時間とともに思い出すのに時間がかかるようになります。
そこで考えるべきは、授業で覚える知識は、生きるため、という点において必要か、ということです。
多分多くの人にとってその知識は必要のないものです。
ということは、何度も繰り返さないと忘れてしまうということです。
そこで私たちは、一定の間隔をあけて定期的に同じことを学習し、脳にだます必要があるわけです。
これは生きていくうえで必要な知識、だから忘れないように!と。
復習が記憶定着に効果があると示している論文はたくさんあります。
また、復習することでテストの点数が上がる、というデータを示したものもあります。
どのように復習をすればいいのか
復習は自分の理解したことの整理や、覚えたことの定着が目的です。
復習の方法をいくつか紹介します。
- その日授業で取ったノートを音読する
- 解いた問題をもう一度解いてみる
- 習ったことを誰かに喋る
- 理解したことを自分の持っている知識と結び付けてみる
- 定期的に脳を休める
結論:予習と復習どちらが大切なのか
予習をしていたグループの方が復習をしていたグループよりテストで高得点を取ったといった研究があったり、復習をすることでテストの点数が上がったという研究結果があったりと、どちらが良いというのは一概には言えそうにありません。
極端な話、
準備をせずとも優れた理解力でその授業の中ですべてを理解できるのであれば予習は必要ありません。
驚異的な記憶力があり、何も忘れないのであれば復習の必要はありません。
しかし、多くの生徒がそれには該当しないはずです。
5分の予習が授業の理解度を30パーセント程度向上させ、10分の復習が定期考査前の勉強を1時間短縮させることができるかもしれない、と思えば、予習と復習をやろう、と思う生徒は増えるはずです。
教員は、予習と復習が具体的にどのようなメリットがあるのかを伝え、そのうえで生徒に能動的な学習計画を立てさせるのが重要なのではないでしょうか。