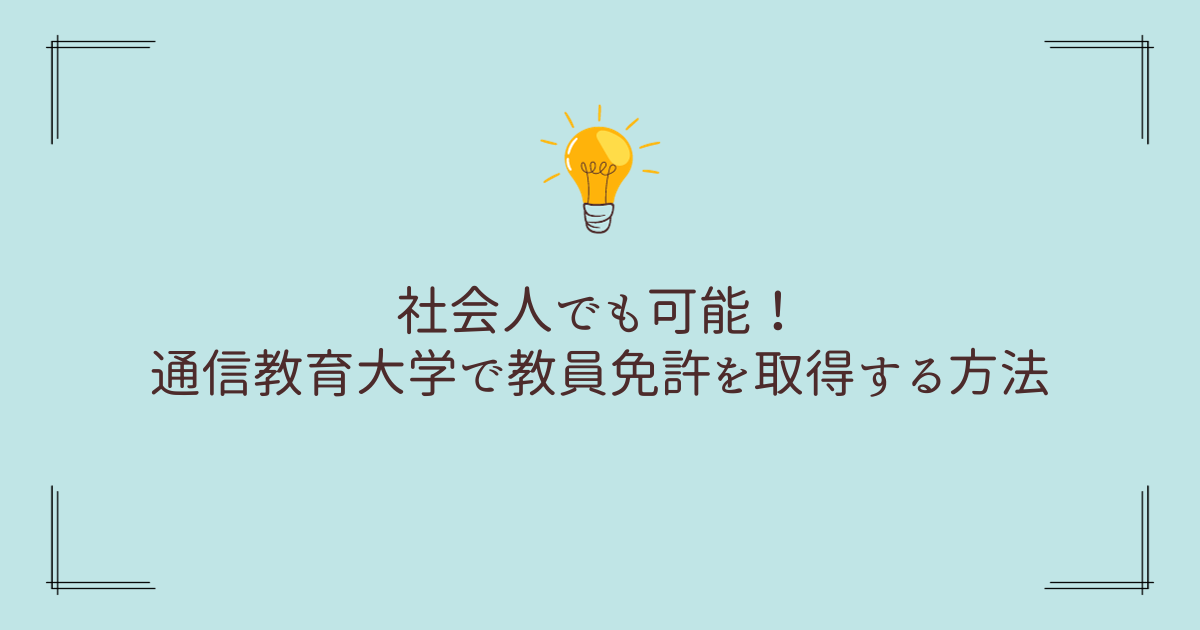アオパパ先生は大学生の頃から教員を目指していたんですか?
いいえ、実は教員を目指したのは大学を卒業して、民間企業で働き始めてからなんです。
そうなんですね!どうやって教員免許状を取得したんですか?
私は日大の通信教育で教員免許状を取りました。
へー!詳しく教えてください!
わかりました。それでは教員免許状を通信教育で取得する流れを説明しますね、
どんな単位を履修すればいいの?
教員免許状を申請するためには二つの条件があります。
それは、基礎資格を得ることと、法定最低修得単位数を修める、という2点です。
表であらわすと以下の通りです。私は英語科の教員免許を取ったので、それをベースに説明します。

教科に関する科目とは、「英語学」や「英文法」などの各教科の専門知識を養う科目を指します。
教職に関する科目とは「発達と学習」や「教育実習」などの教員になるために必要な知識や専門的力量を養う科目を指します。
教科又は教職に関する科目とは上記の両方で教員免許状取得に必要な単位数を充足したうえで更に修得しなければならない単位です。
ここで注意が必要なのが、中学と高校では教職に関する科目で取らなければならない最低単位数に違いがあるということです。
中学校の教員免許を取得するための法定最低修得単位数を修得することができれば高校の教員免許状を取得することはできます。
しかし、高校の教員免許状を取得するための法定最低修得単位数にのっとって単位を修得した場合は中学校の免許状を取得することはできません。
前の大学で修得した単位は流用できる?
結論、できます。
しかし、教員免許状の申請に使える単位は、文部科学大臣が適当と認める大学の課程《認定課程》や、これに相当すると認められる課程で修得したものでなければなりません。
例えば海外の大学で同じような科目を修得していたとしても、それが教員免許状の申請に使える単位かどうかは、教育委員会に確認する必要があります。
また、同じ日本の大学でも科目名が違ったり法改定前に履修した科目であったりすると認められなかったりしますので注意が必要です。
昔在籍した大学で修得した単位が最低単位数のどれに該当するか、というのは「学力に関する証明書」というものを発行してもらえばわかります。
私は日大通教入学後すぐに前の大学に「学力に関する証明書」の発行依頼をして、どの単位を取らなければならないのかを精査しました。
結果として体育や外国語コミュニケーション、教科に関する科目を少々修得していたことがわかり、その分は日大通教で修得しなくて良いことになりました。
計画を立てる
さて、自分がどの単位をどれくらい履修しなければならないかがわかったら、免許状を取得したいタイミングから逆算して履修計画を立てます。
科目習得試験やスクーリングのタイミング、自分自身の予定などで、なかなか思い通りに単位修得の目途が立たないこともあると思います。
そんな時はあまり焦らず、自分の人生計画と照らし合わせて計画を立てるのがよろしいかと思います。
ただし、初めて教員免許を取得する場合そうも言ってられないタイミングが訪れます。
それが教育実習です。
仕事をしながらの教育実習は大きな壁
通信大学で学ぶ人の中には、仕事と学校を両立している方もいらっしゃると思います。その場合2~3週間程度連続して休まなければならない教育実習はかなりハードルが高くなります。
私自身、教育実習のタイミングで前の職場に退職する旨を伝えました。
幸いその時は3週間まるまる有休を使うという処置をとることができましたが、通常ですとなかなか厳しいのではないかと思います。
しかし!この教育実習をやらなければ自分の夢を諦めることになってしまいます。
今の仕事も大切だとは思いますが、やりようはあると思いますので是非頑張っていただければと思います。
その後
教育実習を無事終えることができ、法定最低修得単位数も修得し終われば、後は自分の住んでいるところの教育委員会に免許状を申請するのみです。
申請方法につきましてはご自身が住まわれている都道府県の教育委員会のホームページに詳しく載っているかと思いますのでそちらを検索してみてください。
以上が初めて教員免許を取得する場合の大まかな流れになります。
思った以上に多くの科目を履修しなければならなかったり、時間の確保を余儀なくされる教育実習があったりとハードルが高くうつるかもしれませんが、強い思いがあればなんとかなります。
この記事を読んで少しでも多くの人が働きながら免許状取得を目指すきっかけになれば幸いです。