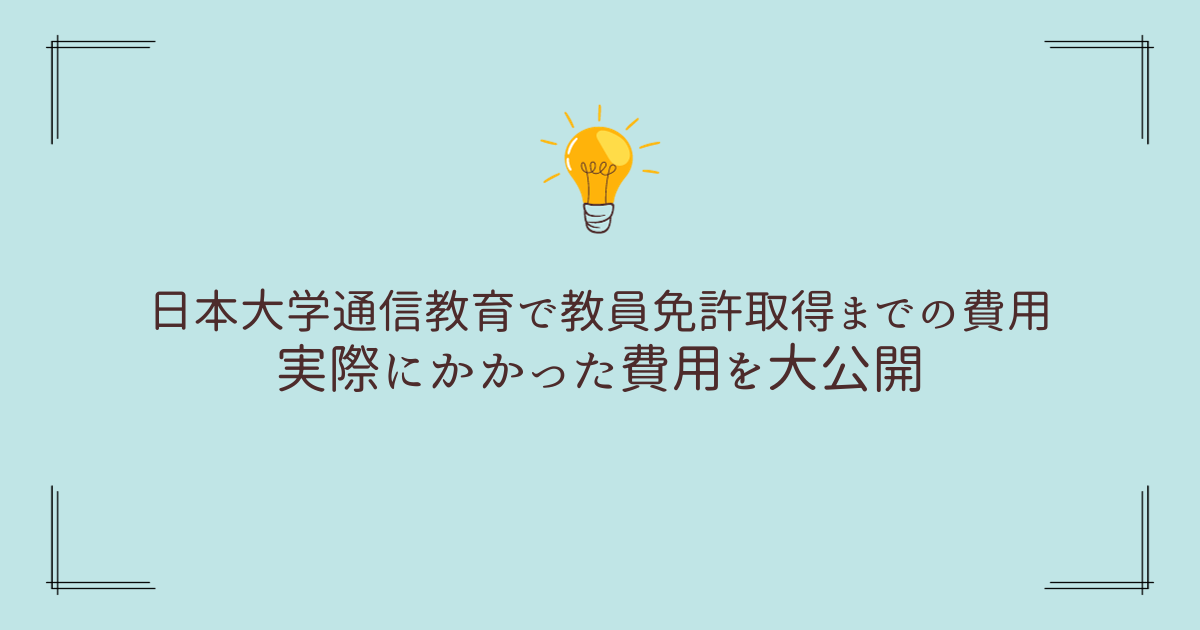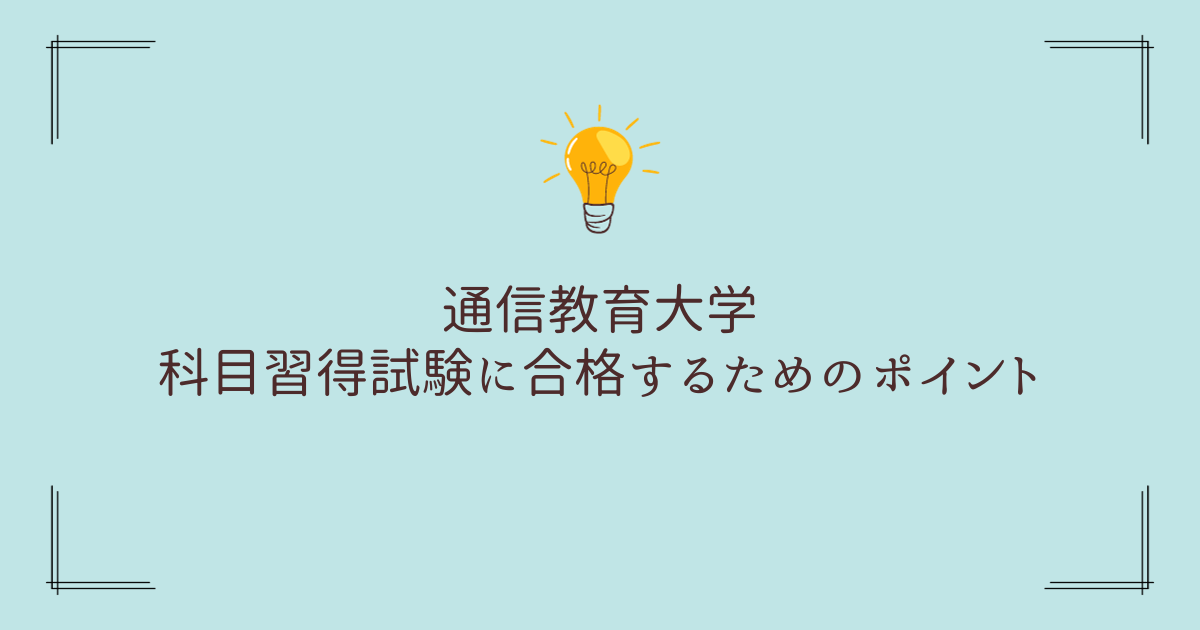通信教育で単位を取る場合って、レポートを書かないといけないんですよね?どのくらい書いたんですか?
教員免許を取るために、13冊レポートを書きました。
そんなに書いたんですね!何かコツはあるんですか?
コツというかレポートを書く上で大事なことがいくつかあります。それを守れば不合格になることはまずないでしょう。
そうなんですね!是非教えてください!
レポートを書く上で大事なこと
レポート課題をよく読む
当たり前のことかもしれませんが、与えられた課題がどういうもので、どのように答えればいいのかをまず考えます。
ピンとこない方もいるかもしれませんので、英米文学概説で課された課題を例にご説明します。
【課題】
「教材の第1章を読んで、著者が主張する”precision”の特性について、文学作品から引用しつつ、論述しなさい。」
さあ、どうでしょう。
この課題に対して、まず”precision”について論述しなければ間違いなく不合格になりますよね。
他にも“著者が主張する“と書いてあるので、自分自身が勝手に考えた”precision”を書いてもダメなことがわかります。
さらには“文学作品から引用しつつ”とも書いてありますので、文学作品から引用しなければ不合格になるということも注意しなければなりません。
設問に書いてある指示を無視すれば基本的にそのレポートは不合格です。
極端な話、横書き指定の課題に対して縦書きで書いて提出したら一発でアウトです。
そして、書いている途中で、あ、こんなことも書いてあった!と思っても後から付け加えるのは至難の業ですし、そもそも文の構成がおかしくなってしまう可能性が高いです。
それを避けるにも、まずレポート課題をしっかり読み、どういう指示のもと、どういうことを聞かれているのかを整理してから書き始めることが大切です。
必要な情報を揃える
レポート課題を読んだら、いきなり文章を書き始めるのではなく、レポートを書き上げるための情報が手元にあるかどうかを確認します。
先ほどの例を再度取り上げますが、まずレポートに取り組むには”教材の第1章”を読んでいなければレポートは書けません。
また、著者が主張する”precision””とは何なのかをわかっていなければ書けません。
更に言うと、著者が主張する”precision”がうまく表れている文学作品を探しだす必要もあります。
教科書の中にある情報だけでは足りないな、と思ったらインターネットで検索するか、ほかの書籍を自分で探して読んでみるという作業も必要になってきます。
このようにしてレポートを書き上げるにあたって必要な情報をまず手元に揃えます。
これを怠ると、2,000文字のレポートを書くのが難しくなってしまいます。
逆にこの部分の情報収集がしっかりできていれば、あとはパズルを組み立てるみたいに必要な情報を構成通りに並べていくだけですので、あっという間に2,000文字に到達します。
レポートの構成を考える
レポートは日記とは違います。
レポートは誰かに読んでもらうことを想定した文章です。
誰かに読んでもらう文章ということは、ルールに沿って文章を組み立てる必要があります。
もしそのルールを無視してしまうと、とても読み辛い文章になってしまい、採点に悪い影響を与えてしまう可能性があります。
一般的なルールとしては、序論、本論、結論の三大構成法で書く場合が多いとされています。
他には起承転結の四段構成法や、序論、説話、論証、列叙、結論の五段階構成法なんかも存在しますよね。
どのルールで組み立てても良いと思いますが、私は基本的に三段構成法でレポートを作成していました。
ルールと言えば、引用したら引用個所を示したり、レポートの末に引用・参考文献として載せるというのもルールですので、そこもしっかり守っていました。
誰が読んでも理解できる文書を心がける
レポートを書き始めると、あえて難しい言葉を使ったり、無駄な形容詞を付けたり、わざと長ったらしい文書を書いたりしてしまいがちですが、そういう文章は読み辛いです。
どうしても難しい専門用語を使いたい!と思った時は、この専門用語はこういう意味で使っているのですよ。という説明を入れて使っていました。
そうすることで採点者に対しても、私ちゃんとこの用語の意味理解してますよ、というアピールにもなります。
まとめ
私はレポートを書く際に以上の4点を意識して書きました。結果として不合格になったレポートは1つもなかったので、レポートの書き方としては間違っていなかったと言えます。
ですので、もしレポート書くのが苦手だなーという方がいらしたら是非参考にしてみてください。