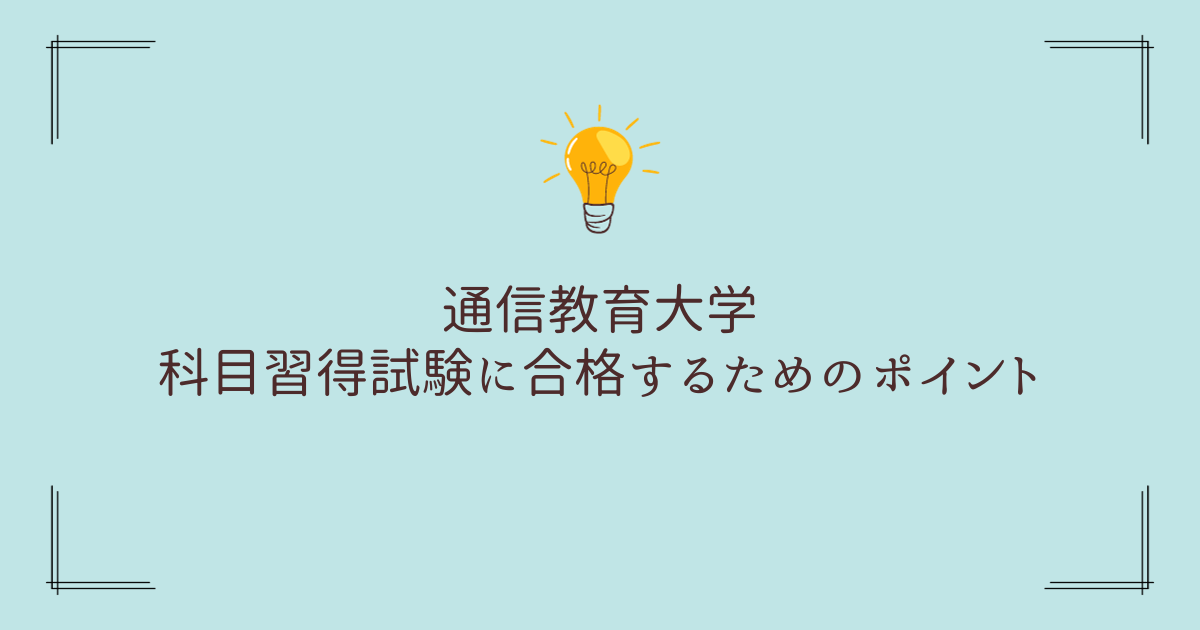通信大学で単位を修得するには自宅学習が基本になります。
一般的にはまずレポートを所定の期限までに提出し、科目習得試験を受けます。
この試験が自宅学習の成果を試す場となります。
そしてこの試験、準備不足だと平気で不合格になります。
そこで今回は私の苦い経験も含めてこの科目習得試験の準備方法をお伝えしたいと思います。
科目習得試験とは
大学によっては科目終了試験とも言うみたいですが、科目習得試験とは教科書の学習成果を判定し、単位を修得するための試験を指します。
また、1回の試験で受験できる科目数は4科目までとなっています。
※後で言及しますが1度に4科目受けるのは相当しんどいです。
試験実施日
日大通教の場合、1年間に4回実施します。
※入学初年度は最大でも3回の受験機会となります。
試験会場は日本国内で約50か所(平成27年度)とのことです。
試験実施月とレポート提出の目安

受験対策
過去問題から問題をリストアップ
受験対策は過去問を入手し、問題の傾向を捉えて、対策を練るのが一番です。
例として「生徒指導・進路指導論」で説明します。
下記の表が平成27年と平成28年の過去出題された問題です。

全く同じ問題が出題されていることもあり、過去問の重要性がわかっていただけたかと思います。
そして、過去問と教科書を照らし合わせて出題されそうなテーマを選出します。
生徒指導・進路指導論で考えると以下の4テーマに応えられるように準備しておけば大丈夫、ということになります。
・生徒指導の意義・目的・必要性
・生徒指導の方法
・進路指導の意義・目的
・キャリア教育の意義、導入の背景
このようにして、膨大な試験範囲のなかからテーマを抽出して試験対策を行います。
過去問は日大通教の通信教育部キャンパスに行けば過去3年分を参照することができます。
また、過去1年分の問題が収録された「科目習得試験問題集」が水道橋の丸沼書店というところで販売されています。
ここで1点注意点があります。
問題の傾向は突然変わる可能性もあります。
どんな時かというと出題者が変わった場合です。
実はこの生徒指導・進路指導論も平成29年は出題者が変わり問題の傾向もガラッと変わりました。
私はそこに気づかず上記のテーマで対策していた為痛い目を見ました。
というか1度不合格になりました。
過去問がない場合の試験対策として有効なのは日大通教から送られてくる「科目習得試験の手引き」という冊子です。
科目によっては担当教員から学習上のアドバイスなどもありますので、そちらを参考にして試験対策を練ります。
試験当日について
試験会場では各人に問題冊子と答案用紙が配布されます。
1科目当たりの試験時間は60分間となっております。
ここでのポイントは以下の2点です。
・わからなくてもとにかく書く
・出題された問題をよく読み、それに対して答える。
しっかり試験対策したとしても試験範囲が膨大なため当てがはずれることもあります。
それは仕方のないことです。
しかし問題を見てすぐあきらめてしまうのではなく、自分の準備してきた内容と問題をうまくリンクさせて、とにかく書くことをお勧めします。
白紙で提出すれば確実に不合格ですが、何か書いてればもしかしたら合格をもらえるかもしれません。
どんな試験でも共通しますが、出題された内容に答えるのは大切です。例えば上の例で挙げた問題で、「生徒指導の方法を説明しなさい。」というのがありましたが、この問題に対していくら生徒指導の素晴らしさを書いても合格はもらえません。試験問題に対してポイントをしっかり絞って簡潔にそして明瞭に答えることが大切です。
試験が終わったら
あとは合格を祈るのみ!
落ちているかもと思ったら次の試験に向けて、少しずつでもいいので対策を練るといいかもしれないですね。